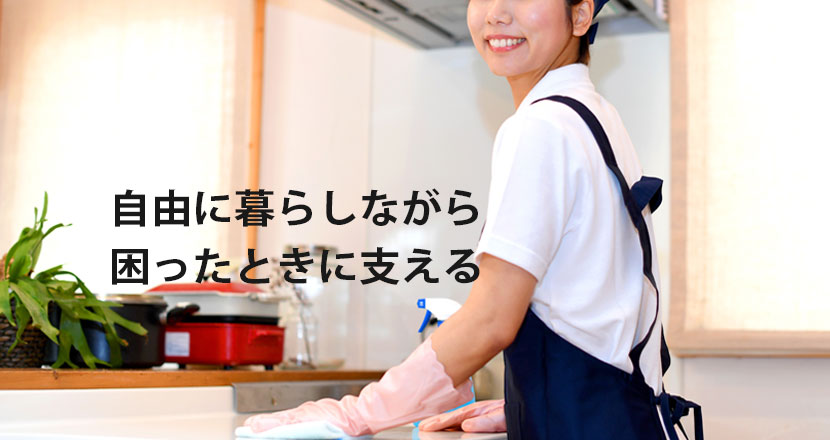イチイが取り組む「分散型サ高住の事業化」についてご報告します。
(前回よりつづく)
見守りスタッフのいつ場所が高齢入居者のスペースに
生活支援サービスを提供できるかが事業成功のカギ
それでは、分散型サ高住がユーザーから望まれる理由について以下にご説明します。
➊友人のいる住み慣れた街で暮らしたいから
➋負担のかかる広い家を出て、コンパクトでバリアフリーの暖かい住まいに移りたい
➌生活利便性の高い比較的家賃が高額な地域でも家賃がリーズナブル
➍自由に暮らしながらも孤立せず、困ったときに支えてもらえる
そうしたニーズはあるものの、分散型サ高住はなかなか広がりません。
それは入居を検討するユーザーに「最期まで暮らせるのか、生活支援は十分なのか」といった不安があるからです。
困りごと解決などノウハウ不足の事業者
その一方で、供給側の事業者としては次のような点が課題となっています。
➀ハード以外の管理、例えばコミュニティづくりが負担になるのでは、との不安がある
➁困りごとの解決や生活支援のノウハウがない
➂何かあったときの責任など、負担やリスクが読み切れない
分散型サ高住のゴールイメージは、直接的な介護サービス以外のちょっとした困りごとを含む総合的な生活支援サービスが提供され、地域の医療や介護資源を活用しながら、長く住み続けられる住まいをつくることです。
しかしながら、事業者がこの領域を担うには、人件費など経費を賄える大規模な戸数が必要になります。
では、どうすればいいのでしょうか。
〈つづく〉